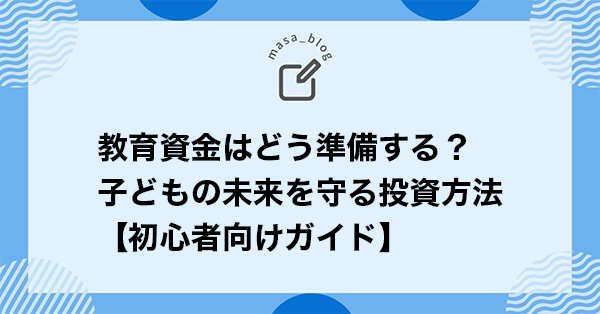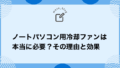子どもの教育資金、どう準備していますか?投資という選択肢もあるんです
「子どもの教育費って、いくらぐらいかかるんだろう…?」
「毎月の生活で精一杯なのに、将来のお金まで考えなきゃいけないの?」

そんなふうに感じたことはありませんか?
最近は、高校や大学の学費がどんどん上がっていると言われています。公立でも数百万円、私立だと1000万円以上かかることもあるんです。
でも、ただ「貯金」するだけでは、将来の物価上昇や教育費の増加に追いつかない可能性も。
しかも、普通預金の金利はほとんど増えないから、お金がなかなか育たないのが現実です。
その結果、
・進学の選択肢を減らさざるを得ない
・奨学金で子どもに負担が残る
という家庭も少なくありません。
そこで今、注目されているのが「教育資金を投資で準備する」という方法です。
といっても、「投資ってこわい」「損しそう」と思うかもしれませんが、時間を味方につけたコツコツ投資なら、誰でもムリなく始められます。
たとえば、つみたてNISAや新NISAといった制度を使えば、少額でも、税金の心配をせずにお金を育てていくことができるんです。
実際に、
「児童手当をそのまま毎月つみたてNISAに回したら、10年で100万円以上増えた!」
「投資初心者だったけど、ネット証券で口座を作って500円から始められた」
という声もたくさんあります。
この記事では、
教育資金のための投資方法をわかりやすく解説していきます。
初心者でも始めやすく、失敗しにくい方法、安心して使える制度、そしてよくある疑問への答えまで、すべて1記事にまとめました。
「子どもに好きな進路を選ばせてあげたい」
「できるだけ早いうちから、ムリなく備えたい」
そんな方にこそ読んでいただきたい内容です。
将来に不安を残さないために、今こそ教育資金の投資について学んでみませんか?
1. 教育資金に向いている投資とは?
子どもの将来のために、大学や専門学校の学費をしっかりと準備したいと考えている親は多いですよね。
でも、毎月ただ貯金するだけでは「本当に足りるのかな…?」と不安になることもあると思います。
そこでおすすめなのが、「投資」を活用してお金を少しずつ増やしていく方法です。

教育資金に向いている投資の特徴とは?
教育資金に向いている投資には、いくつかの特徴があります。
- リスクが少ないこと
教育資金は「何年後に必要になるか」がはっきりしているお金です。だから、ギャンブルのように大きく増える代わりに大きく減る可能性のある投資は向いていません。リスクが少なく、安定してコツコツ増える投資がぴったりです。 - 途中で引き出せること
子どもが何歳のときに、いくら必要になるかはある程度わかりますが、「急な出費」が発生することもあるかもしれません。そんなときにお金を途中で引き出せるようにしておくと安心です。 - 手数料が安いこと
投資には手数料がかかるものもあります。なるべく手数料が安いものを選んで、将来の教育資金にしっかり残せるようにしましょう。
どれくらいの期間で運用すべき?
教育資金の投資では「時間」がとても大切です。できれば子どもが小さいうち、たとえば0~3歳の時期から始めて、10年~15年という長い時間をかけて育てていくのが理想です。
長期間で投資することで、一時的に価格が下がってもその後回復しやすくなりますし、「複利」といって、得た利益が次の利益を生む好循環が生まれます。
投資と貯金のバランスも大切
もちろん、投資だけに全額を入れてしまうのはおすすめできません。いざというときのために、現金の貯金も残しておきましょう。たとえば、半分は普通の貯金、もう半分は投資にまわす、というように「リスク分散」をすると安心です。
このように、教育資金に向いている投資とは「長期・分散・低リスク」がキーワードになります。無理なく始められて、将来の学費にしっかりと備える方法として、投資はとても有効な選択肢です。
2. 教育資金を投資で準備するメリット・デメリット
「教育資金を投資で準備するのって、本当に大丈夫かな?」「失敗したらこわい…」と思う人も多いかもしれません。たしかに、投資にはいい面もあれば注意しないといけない面もあります。
ここでは、教育資金を“投資”で準備するメリット(良いところ)と、デメリット(気をつけたいところ)をわかりやすく説明していきます。
メリット(良いところ)
①銀行よりもお金が増えやすい
まず一番のメリットは、「お金が増えるチャンスがある」ことです。
たとえば、銀行に毎月1万円を10年間貯金すると、合計で120万円になります。でも、普通の貯金では利息がとても少なくて、ほとんど増えません。
それに対して、投資では年に3~5%くらいのペースでお金が増えていくこともあります。たとえば、毎月1万円を10年間、年利3%で投資すると、約140万円くらいになることもあります(もちろん、相場によって変わります)。
長く続ければ続けるほど「複利(ふくり)」の力がはたらいて、どんどんお金が増えやすくなるんです。
②インフレ対策になる
「インフレ」とは、物の値段が少しずつ上がっていくことです。たとえば、昔は100円で買えたパンが、今では120円になっていたりしますよね。
銀行にお金を入れていても、物の値段が上がると、同じ金額でも買えるものが減ってしまいます。でも、投資ならお金が増える可能性があるので、インフレに負けにくくなるんです。
③教育費の大きな負担をやわらげられる
高校・大学・専門学校などの教育費は、年々高くなっています。大学進学だけでも、私立の場合は4年間で平均400万円以上かかるとも言われています。
投資で教育資金を計画的に増やしておくことで、いざというときに「奨学金に頼らなければならない」「学費のためにローンを組む」などの負担を減らすことができます。
デメリット(気をつけるべきところ)
①元本割れ(がんぽんわれ)のリスクがある
「元本割れ」とは、投資したお金が減ってしまうことです。たとえば、10万円を投資していたのに、ある時期に評価額が8万円に下がってしまう…ということも起こりえます。
投資には「リスク」がつきものなので、短期間で結果を出そうとすると、損をすることもあります。
でも、時間をかけてじっくり投資すれば、リスクを減らせる可能性があります。10年、15年という長期の投資がすすめられる理由がここにあるのです。
②必ず増えるわけではない
「投資すれば100%お金が増える」と思っている人もいますが、それは間違いです。世界の経済状況や、企業の業績、政治の動きなどによって投資の結果は大きく変わることがあります。
だから、無理に高いリターンを狙うよりも、「少しずつ、長くコツコツ続ける」ことが大事です。
③心の負担があることも
投資は価格が毎日変わるので、「今日は上がった!」「下がってる…どうしよう」と、気になってしまう人も多いです。とくにお金のことに不安があると、毎日ドキドキしてしまい、ストレスになることもあります。
教育資金という「大事なお金」を投資にまわすのですから、不安になりすぎないように、安心して使える商品(例:インデックス型の投資信託など)を選ぶことが大切です。
メリットとデメリットのバランスをとることが大切
投資には、いいところもあれば、注意が必要なところもあります。だからこそ、投資だけに頼るのではなく、貯金や学資保険などと組み合わせて、「バランスよく準備する」ことが大事です。
たとえば、
- 毎月1万円を投資にまわす
- もう1万円は銀行口座に貯金する
といった感じで、リスクと安定のバランスをとると安心ですね。
まとめ
教育資金を投資で準備することで、お金が増えるチャンスを得られたり、インフレに強くなったりするメリットがあります。でも、必ず成功するとは限らず、元本割れのリスクもあるので、慎重に選ぶことが大切です。
家族でよく話し合って、安心して取り組める方法を見つけましょう。
3. 投資を始める前に知っておきたい注意点
「投資で教育資金を準備したい」と思っても、何も知らずに始めるのはとても危険です。たとえば、知らないまま高いリスクの商品を買ってしまったり、手数料が高い投資を選んでしまったりすることがあります。
ここでは、投資を始める前に「これだけは知っておきたい!」という大切なポイントをやさしく解説していきます。
①投資は「すぐにお金が増えるもの」ではない
投資と聞くと、「株を買ったらすぐに何万円も増えた!」という話を聞くことがあります。でも、それはまれなケースです。
本来の投資は「長い時間をかけて、コツコツ増やしていくもの」です。教育資金も、子どもが生まれたときから10年以上かけて準備するケースが多いので、急がず、じっくり進めることがポイントです。
短期間でお金を増やそうとすると、そのぶんリスク(損する可能性)も高くなるので注意しましょう。
②「元本保証(がんぽんほしょう)」はない
貯金や定期預金とはちがって、投資には「元本保証(がんぽんほしょう)」がありません。つまり、投資したお金が必ず戻ってくるとは限らないのです。
たとえば、10万円を投資信託で運用しても、相場が悪ければ8万円に減ってしまうかもしれません。
だからこそ、投資に使うお金は「生活に必要な資金」とは分けて、「なくなっても生活に困らない余裕資金」で行うのが基本です。
③手数料や税金の仕組みを知ろう
投資には、「買うとき」「売るとき」などに手数料がかかることがあります。また、利益が出た場合には税金がかかることもあります。
たとえば、株を売って利益が出ると、約20%の税金が引かれます。100万円の利益が出ても、手元に残るのは約80万円です。
また、投資信託やロボアドバイザーなどのサービスも、運用にかかる「信託報酬(しんたくほうしゅう)」などの手数料があります。なるべく手数料の安い商品を選ぶと、お金が減りにくくなります。
④投資の種類をしっかり理解する
投資にはいろいろな種類があります。たとえば…
- 株式(会社の株を買って、その会社の成長にかける)
- 投資信託(いろんな会社の株や債券を、プロがまとめて運用してくれる)
- 債券(国や会社にお金を貸して、あとで利息つきで返してもらう)
- 不動産投資(アパートやマンションを買って、家賃収入を得る)

教育資金に向いているのは、比較的リスクが低めで、長期で運用できる「投資信託」や「つみたてNISA」などです。
「これなら安心して長く続けられるな」と思えるものを選びましょう。
⑤必ず自分で調べてから始める
「友達がすすめてくれたから」「インフルエンサーが言ってたから」という理由で投資を始めるのはとても危険です。人によってお金の考え方や生活の状況はちがうので、他人の意見だけで決めてしまうと、あとで後悔するかもしれません。
ネットにはたくさんの情報がありますが、信頼できる金融機関や公式サイト、ファイナンシャルプランナーのアドバイスなどを参考にして、自分の目で確かめましょう。
⑥投資詐欺に注意!
最近では、「絶対に儲かります!」「元本保証で年利10%!」という、うますぎる話でだます「投資詐欺」がふえています。
こういった話は、ほとんどがウソか危ない仕組みです。とくに、「子どもの将来のために」と思って大金をだまし取られる人もいます。
- 「必ずもうかる」
- 「ノーリスクで高リターン」
- 「限定募集、今だけ」
などの言葉が出てきたら、まずは疑ってください。少しでも不安を感じたら、家族や専門家に相談しましょう。
⑦投資は「目的」を忘れずに
最後に大事なことは、「なぜ投資をするのか?」という“目的”をはっきりさせておくことです。
教育資金のために投資をするなら、「子どもが高校や大学に行く時に必要になるお金を、〇年後までに〇万円そろえる」といった、具体的なゴールを決めておくと迷いません。
その目標に合わせて、どんな投資商品がいいか、どのくらいの金額をどのくらいの期間続けるのか、計画を立てていきましょう。
まとめ
投資を始める前には、リスク、手数料、税金、そして目的をしっかり理解しておくことがとても大切です。「よく知らないまま始めてしまって、あとで困った…」ということがないように、まずは小さく始めて、少しずつ学びながら進めていきましょう。
4. 教育資金の投資におすすめの商品を紹介
「投資」と聞くと、むずかしそうに感じるかもしれません。でも、教育資金のように「○年後に必要になるお金」を準備したいときに向いている投資商品は、実はある程度決まっています。
この章では、初心者でも安心して始めやすく、教育資金の準備にもぴったりな投資商品をわかりやすく紹介していきます。
①つみたてNISA(ニーサ)
まず最初に紹介したいのは「つみたてNISA(少額投資非課税制度)」です。
これは、毎月少しずつお金を投資していく仕組みで、「投資で得た利益に税金がかからない」というメリットがあります。ふつうは、投資で利益が出ると約20%の税金がかかりますが、つみたてNISAではそれが「ゼロ」になるのです。
◎なぜ教育資金に向いているの?
- 毎月コツコツ積み立てる仕組みだから、長期的な資金準備にぴったり
- 金融庁が選んだ「安心して長く続けられる投資信託」だけに投資できる
- 最長20年間、運用益が非課税(税金ゼロ)
子どもが小さいうちから始めておけば、大学入学のころにはまとまったお金になっている可能性が高いです。
②ジュニアNISA(※2023年終了/代わりに親のつみたてNISAを活用)
ジュニアNISAという制度は2023年で新規の受付が終了しましたが、すでに始めている人は2024年以降も使えます。
現在は、親が自分の名義で「つみたてNISA」を活用し、将来子どものために使うという形が主流です。子ども名義にこだわらず、目的に合わせて資金を分けて管理する工夫が大切です。
③投資信託(とうししんたく)
投資信託は、たくさんの人から集めたお金を、プロがまとめていろいろな株や債券に分散して投資してくれる商品です。
とくに教育資金には「バランス型」の投資信託が人気です。これは、株と債券の両方に投資していて、値動きのバランスがとれているため、リスクが高すぎず低すぎず、安定的にお金を育てられます。
◎おすすめポイント
- プロが運用してくれるから初心者でも安心
- 少額からでも始められる(100円~1,000円でOKな場合も)
- 分散投資だからリスクが低め
つみたてNISAで投資できる商品も、ほとんどがこの「投資信託」です。
④個人向け国債(こくさい)
「絶対に元本を減らしたくない」「もっと安全に投資したい」という人には、「個人向け国債」がおすすめです。
これは、国(日本)が発行する債券(お金を借りるための証明書)で、満期まで持てば元本(最初に出したお金)が必ず戻ってきます。銀行の定期預金よりは少しだけ利息(もうけ)が高く、安全性が高いのが特長です。
ただし、利回りはとても低いため「お金を大きく増やす」目的ではなく、「減らしたくない」という人向きです。
⑤ロボアドバイザー
最近は、投資を自動でやってくれる「ロボアドバイザー」も人気です。質問に答えるだけで、その人に合った資産運用プランをつくってくれて、あとはロボットが自動で運用してくれます。
たとえば…
- Wealnavi(ウェルスナビ)
- THEO(テオ)
- 楽ラップ
などがあります。
ただし、ロボアドバイザーは運用の手数料がやや高め(年1%前後)なので、長期的には投資信託の方がコストパフォーマンスが良いケースもあります。
⑥ iDeCo(イデコ)は教育資金には不向き
「つみたてNISAとiDeCo、どっちがいいの?」と迷う方も多いですが、iDeCo(個人型確定拠出年金)は教育資金には向きません。
なぜなら、原則、60歳までお金を引き出すことができないからです。教育費は子どもが18歳~22歳くらいまでに必要になることが多いため、60歳以降でないと使えないiDeCoは不便です。
iDeCoは「老後資金」のための投資制度と考えましょう。
⑦おすすめの組み合わせ
教育資金のために投資を始めるなら、次のような組み合わせがおすすめです。
例:月2万円を10年間積み立てたい場合
- つみたてNISAで投資信託に月1.5万円
- 残り5,000円は普通預金や定期預金で安全に管理
このように、投資と貯金をバランスよく使い分けると、リスクをおさえながら効率的に教育資金をためることができます。
まとめ
教育資金の準備には、つみたてNISAや投資信託といった「長期運用に向いている商品」を選ぶのがポイントです。大事なのは、「よくわからないからやらない」ではなく、「安心して少しずつ始めてみること」です。
商品選びに迷ったときは、信頼できる金融機関の窓口や、ファイナンシャルプランナーに相談してみるのも良いでしょう。
5. 子どもの年齢別!教育資金投資のタイミングと戦略
教育資金を準備するときに大切なのは、「いつ、どのくらいのお金が必要になるか」をしっかり考えることです。
投資はすぐにお金が増えるものではありません。時間をかけて、じっくり育てていくものです。だからこそ、子どもの年齢に合わせて「今どんな投資をすればいいか」を考えることがとても重要です。
この章では、子どもの成長段階(年齢別)に分けて、教育資金の投資戦略を解説します。
◆ 0歳~5歳(未就学児)|もっとも有利なスタート時期
この時期は教育資金を最もじっくり準備できるタイミングです。高校や大学入学までに10年以上あるため、長期投資にぴったり。
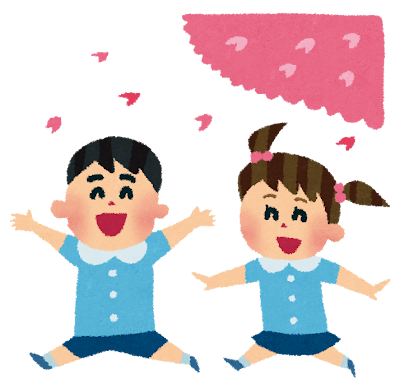
●戦略のポイント
- 積立投資の開始にベストなタイミング
- 多少の値動きがあっても、時間がカバーしてくれる
- リスクをとった分だけ、将来のリターンが期待できる
●おすすめの方法
- つみたてNISAで投資信託をスタート
→ 株式メインの投資信託もOK。長期運用で増える可能性あり。 - 月々1万円~2万円を10年超のスパンで積み立て
(例)月2万円 × 18年(0歳から大学入学まで)
→ 年利5%で運用できた場合、およそ690万円になります!
この時期に始めることが、将来の教育費負担をぐんと軽くしてくれます。
◆ 6歳~12歳(小学生)|コツコツ継続しながら一部安全資産へ
小学生になってくると、大学まであと10年ちょっと。まだ十分な時間はありますが、将来のお金を使う時期が少しずつ近づいてきます。

●戦略のポイント
- 株式中心のリスク資産を持ちながらも、安全資産(預金など)を少し増やしていく
- 投資のバランスを「守り」にも寄せていく準備を始める
●おすすめの方法
- つみたてNISAは継続
- バランス型投資信託(株+債券)を選ぶのもアリ
- 教育費の一部は定期預金や学資保険など、元本保証型に切り替えるのもOK
【注意点】
- 高学年になるほど使うお金のタイミングが近づく
- 「何年後にいくら必要か?」を逆算して計画することが大切です
◆ 13歳~15歳(中学生)|リスク調整と現金化の準備
この時期になると、大学進学まであとわずか。あと5年もすればまとまったお金が必要になります。

●戦略のポイント
- 株式中心の投資信託から、債券型や預金型にシフトしていく
- 少しずつ投資のリスクを下げることが大切
●おすすめの方法
- つみたてNISAは続けるが、「元本割れしにくい商品」に見直す
- 一部は普通預金や定期預金に移す
- お金が必要なタイミングから逆算して、3~5年前には現金化を始める
(例)中学1年生の時点で100万円投資していた場合
→ 高校卒業(6年後)で使うなら、3年後あたりから取り崩し開始がベスト
◆ 16歳~18歳(高校生)|現金化&使い方の計画を
この時期になると、大学入学の費用が目の前です。受験、入学金、引っ越し費用など、急にお金が必要になるタイミングでもあります。

●戦略のポイント
- ほぼすべての資産を安全な状態にしておくことが大切
- 現金化した資金を、すぐ使える形で保管(普通預金など)しておく
●おすすめの方法
- すでに投資していた資金は、タイミングを見て売却
- 売却後は、使い道別に分けて保管(学費・生活費・予備費など)
- 必要なお金は、無理に投資で増やそうとせず、使うために残す!
まとめ
| 子どもの年齢 | 投資スタイル | 戦略のポイント |
| 0~5歳 | 株式中心の長期積立 | 成長を重視して積極的に |
| 6~12歳 | 株+債券バランス型 | 少しずつリスク調整開始 |
| 13~15歳 | 債券重視へシフト | 現金化の準備を始める |
| 16~18歳 | 完全な現金保有 | すぐ使える状態にしておく |
教育資金の投資は、「始めるタイミング」と「終わらせるタイミング」の両方が大事です。とくに子どもの年齢によって戦略を変えることが、失敗しないためのカギになります。
「投資=お金を増やす手段」ですが、教育資金は「使う予定が決まっているお金」です。増やしすぎず、減らしすぎず、必要なタイミングでちゃんと使えることが一番大事です。
6. 教育資金を投資で準備する際の注意点とリスク
教育資金を投資で準備するのはとても効果的な方法ですが、「絶対にうまくいく」とは限りません。なぜなら、投資にはリスク(危険)があるからです。
大事なお金を使って投資をするのですから、失敗しないように気をつけるポイントをしっかり知っておきましょう。
ここでは、教育資金を投資で準備する際に気をつけたい「注意点」と「リスク」をわかりやすく解説します。
◆教育資金投資で気をつけるべき3つのリスク
①元本割れのリスク(お金が減ってしまう)
投資には「元本割れ」というリスクがあります。これは、最初に出したお金よりも少なくなってしまうことです。
たとえば、100万円投資したのに、株価が下がって80万円になってしまった…というようなことが起こるかもしれません。
教育資金は「絶対に必要なお金」なので、使う時期が近くなったらリスクの低い運用に切り替えることが大切です。
②タイミングのリスク(使いたい時に値下がり)
もうひとつ注意したいのが、「タイミングのリスク」です。
投資しているお金が、使いたいときにちょうど下がっていたらどうしますか?
たとえば、大学の入学金を払う直前に、株価が暴落してしまったら、大きな損を出す可能性があります。
このリスクを減らすには、「数年前から少しずつ現金化していく」のがポイントです。
③感情に流されるリスク(焦って間違える)
投資では、「ニュースを見て焦って売ってしまった」「みんなが買っているから自分も買った」など、感情に流されて失敗してしまうケースもあります。
教育資金は冷静に計画的に運用する必要があります。焦って動いてしまうと、かえって損をすることがあるので注意が必要です。
◆教育資金投資で気をつけるポイント
①使うタイミングを決めておく
教育資金は「何歳のときに、いくら必要か」がある程度決まっています。
たとえば:
など、必要な時期がわかっていれば、「その○年前までには現金に戻しておこう」という判断がしやすくなります。
②途中で投資額を見直す
収入や家計の変化によって、「毎月の積立額を増やす」「一部をやめる」などの見直しが必要になることもあります。
定期的に(年に1~2回)自分の投資状況を確認して、「このままで大丈夫かな?」とチェックするようにしましょう。
③元本保証の商品とバランスをとる
すべてをリスクのある商品にするのではなく、一部は「元本保証」のあるもの(定期預金や学資保険など)にするのもおすすめです。
たとえば:
というように、リスクを分散することで、安全性が高まります。
◆投資詐欺や誤った情報にも注意!
教育資金を投資で準備する人が増えてきたことで、最近では「高いリターンをうたった投資詐欺」も増えています。
たとえば:
といった言葉には要注意。高すぎる利益の話は、要注意!です。
信頼できる証券会社や金融機関を使い、情報も金融庁やNISA公式サイトなど、正しい情報源から得るようにしましょう。
◆投資以外にも準備方法を組み合わせよう
投資だけに頼るのではなく、他の方法と組み合わせることも重要です。
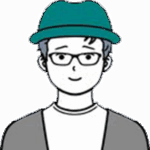
私も学資保険があったので助かりました。でも、それだけでは全然足りないんです!
まだ、「先の話だから」、「何とかなるだろう」とか、甘い考えではいずれ後悔します。後悔しないためにも、早めに準備を始めた方が良いですよ!
これらを投資と組み合わせれば、安定性と成長性のバランスがとれた準備ができます。
まとめ
教育資金を投資で準備するのはとても効果的ですが、リスクもあります。
大切なポイントは以下の3つです。
- 使う時期を決めて、計画的に投資すること
- リスクの高い商品ばかりにしないこと
- 定期的に見直しを行うこと
「投資だから失敗しそう」と不安になるかもしれませんが、リスクを知っていれば、きちんと対策ができます。
冷静に計画して進めれば、教育資金をしっかり準備することができますよ。
7. 教育資金の投資に関するよくある質問(FAQ)
教育資金を投資で準備しようと考えていると、「これで本当に大丈夫かな?」と不安に感じることがあるかもしれません。ここでは、実際によくある質問と、その答えをわかりやすく紹介します。
投資がはじめての方でも安心して進められるように、一つひとつていねいに解説していきます。
- Q子どもが小さいうちから投資を始めた方がいいの?
- A
はい、小さいうちから始めるのがとてもおすすめです。
なぜなら、投資では「時間」がとても大切だからです。時間がたくさんあればあるほど、教育資金が増えるチャンスが広がります。
たとえば:
- 0歳から投資を始めれば、大学入学まで18年
- 小学3年生からでも、あと10年くらいは運用できる
このように、早く始めれば始めるほど、リスクを少なくしながら増やすことができるのです。
- Q投資ってお金持ちじゃないとできないの?
- A
いいえ、少額からでも始められます。
「投資=お金持ちの人がやるもの」と思われがちですが、月100円、月500円からでも始められる証券会社が増えています。
たとえば:
- 楽天証券やSBI証券などでは、ポイント投資も可能
- 月1,000円くらいの少額からでもOK
「できる範囲からコツコツ続けること」が、教育資金の投資では大切なんです。
- Qもし投資が失敗したら、教育資金はどうすればいいの?
- A
教育資金は「確実に必要なお金」なので、投資だけに頼らず、リスクを分散して準備するのがおすすめです。
具体的には:
など、「複数の方法を組み合わせる」ことで、たとえ投資で一部失敗しても他の方法でカバーできるようにしておくと安心です。
- Q投資信託ってどんな商品を選べばいいの?
- A
初心者の場合は、「全世界株式」や「S&P500」など、たくさんの会社に投資できる分散型の投資信託が人気です。
ポイントは:
また、つみたてNISAの対象になっている商品は、金融庁が基準を設けているため、比較的安心して選べます。
- Qお金を使いたい時期が近づいたらどうすればいい?
- A
使いたい時期(たとえば高校・大学入学の2~3年前)になったら、少しずつ投資から現金に戻していくのが安心です。
理由は、「使う直前に価格が下がる」と困るからです。
こうした方法で、安全に資金を確保しましょう。
- Q投資をする時に相談できる相手はいるの?
- A
証券会社や銀行の窓口でも相談できますが、最近は無料のFP(ファイナンシャルプランナー)相談を活用する人が増えています。
「誰に相談していいかわからない…」という方は、中立な立場のFPに一度相談してみるのも良い選択です。
- Q投資で増えたお金には税金がかかるの?
- A
「つみたてNISA」や「新NISA」などの制度を使えば、税金がかからない(非課税)ので安心です。
基本的に投資で利益が出た場合には20.315%の税金がかかりますが、「つみたてNISA」や「新NISA」などの制度を使えば、税金がかからない(非課税)ので安心です。
たとえば、つみたてNISAで年間20万円の利益が出たとしても、通常なら約4万円の税金がかかるところが、NISAなら0円になります。
まとめ
教育資金を投資で準備するのは、早く始めて計画的に進めればとても安心な方法です。
よくある質問のポイントをふり返ると:
というように、ムリなく、ムダなく、安心して準備を進めるコツがたくさんあります。
子供の教育資金のために、無理なく安全に「投資」を始めてみてはいかがでしょうか?
将来、教育資金に苦労しないだけでなく、自らも余裕のある生活が送れるでしょう!